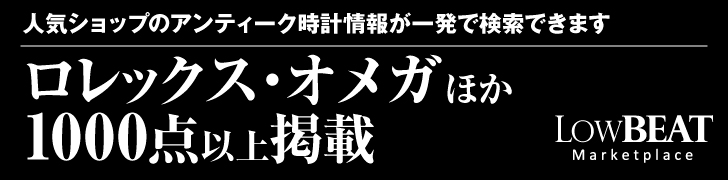アンティーク時計専門サイト「LowBEAT Marketplace」には、日々、提携する時計ショップの最新入荷情報が更新されている。
そのなかから編集部が注目するモデルの情報をお届けしよう。
ビューレン
スーパースレンダー
今回紹介するのは、1950年代後半にビューレンが製造したスーパースレンダーだ。その名が示すとおり、自動巻き腕時計で薄型化を目指したモデルであり、後の自動巻きクロノグラフの開発にも貢献することとなる技術が盛り込まれた時計であった。
シンプルな筋目仕上げの文字盤に、ダイナミックなフォントが用いられた“スーパースレンダー”の表記が特徴的だ。全体的にキズや打痕などは目立たず、非常に良好な状態を維持している。裏ブタ周りにはサビなどが見られるものの、大きな腐食は目立っていない。ムーヴメントも、気密性の高いスクリューバックのおかげで、腐食や変色は見られず、良好なコンディションを維持している。
そんな本モデルで特に注目すべき点は、搭載されているムーヴメントにある。

【写真の時計】ビューレン スーパースレンダー。SS(34mm径)。自動巻き(Cal.1000A)。1950年代製。14万8000円。取り扱い店/WatchTender銀座
【画像:マイクロローターのムーヴメントや文字盤の状態を確認する(全6枚)】
さかのぼること1954年。ビューレンの技術者、ハンス・コッハーが申請した特許“CH329804A”は、世界初のマイクロローター自動巻き機構に関するものだった。
翌年には、マイクロローターのムーヴメントで名を馳せたユニバーサル・ジュネーブが、よく似た内容の特許“CH329805”を申請している。
しかし、ユニバーサル・ジュネーブはビューレンとの特許紛争で敗訴し、ムーヴメントひとつにつき特許使用料を支払うことに同意した、というエピソードも残されている。
そしてその数年後、57年に発売されたのが、今回紹介する“スーパースレンダー”シリーズだ。
当時のビューレンでは“ミニローター”と呼ばれていたマイクロローター搭載機であり、このモデルに搭載されたCal.1000は、自動巻きムーヴメントがまだ未成熟だった1950年代に、機械厚4.2mmという薄さを実現していたという事実には驚かされる。
このムーヴメントは、分針の役割を担う2番車をオフセットさせない、従来どおりの輪列を採用していながらも、時計の機能をつかさどる部品を全体の3分の2程度までにまとめあげるほどのスペース効率を実現している。そして残ったスペースに、マイクロローターと自動巻き機構を納めることで、ムーヴメント厚を抑えることに成功したのだ。巻き上げ方式には、スライディングピニオンを用いたスイッチングロッカー式の応用ともとれる方式が採用されており、両方向の巻き上げを可能としている。
各所の部品に注目すると、薄型化と耐久性を両立させようとした工夫の数々が見て取れる。
一例として、2重になったクラッチ機能付きの角穴車が挙げられる。これは手巻きの際に自動巻き機構に動力が伝わり、高速で空転してしまうことを防止するための機構であり、ローターの回転数で巻き上げ量を稼ぐスイッチングロッカー式の輪列を保護する目的があったのではないだろうか。こういった機構はオメガのCal.500系や550/560系、ジラールペルゴのCal.880系などでも採用されており、自動巻き腕時計の手巻き時に生じる摩耗などを軽減しようとしていたのではないかと思われる。
とは言え、今回紹介する個体に搭載されるCal.1000は、手巻き機構などがやや無理をした設計であったため、手巻きを多用することはあまり推奨できない。また、潤滑油が乾いてしまった状態では、顕著に巻き上げ効率が下がるという評価もあるため、明らかに駆動時間が短い際などには、早期のメンテナンスをおすすめする。
競合他社と比較しても圧倒的な薄さを実現したこのムーヴメントは、後継機であるCal.1280と合わせて、ハミルトンやドゥゲナ、ブローバなどに供給され、ビューレンの経営を支えることになったのだ。
しかしその後、ビューレンは1969年に発表された自動巻きクロノグラフの“クロノマチック”の共同開発に参加するものの、66年にハミルトンに買収されてしまうのであった。だが、誕生したクロノマチックの基礎設計には、ビューレンの影が色濃く残されており、その設計の優秀さが遺憾なく発揮されていることが感じられるだろう。
【LowBEAT Marketplaceでほかの自動巻きの時計を探す】
文◎LowBEAT編集部/画像◎WatchTender銀座